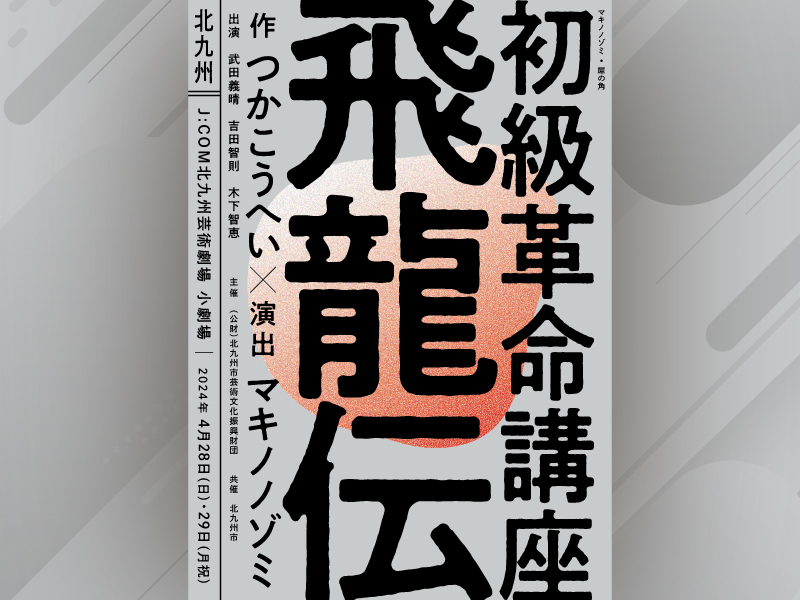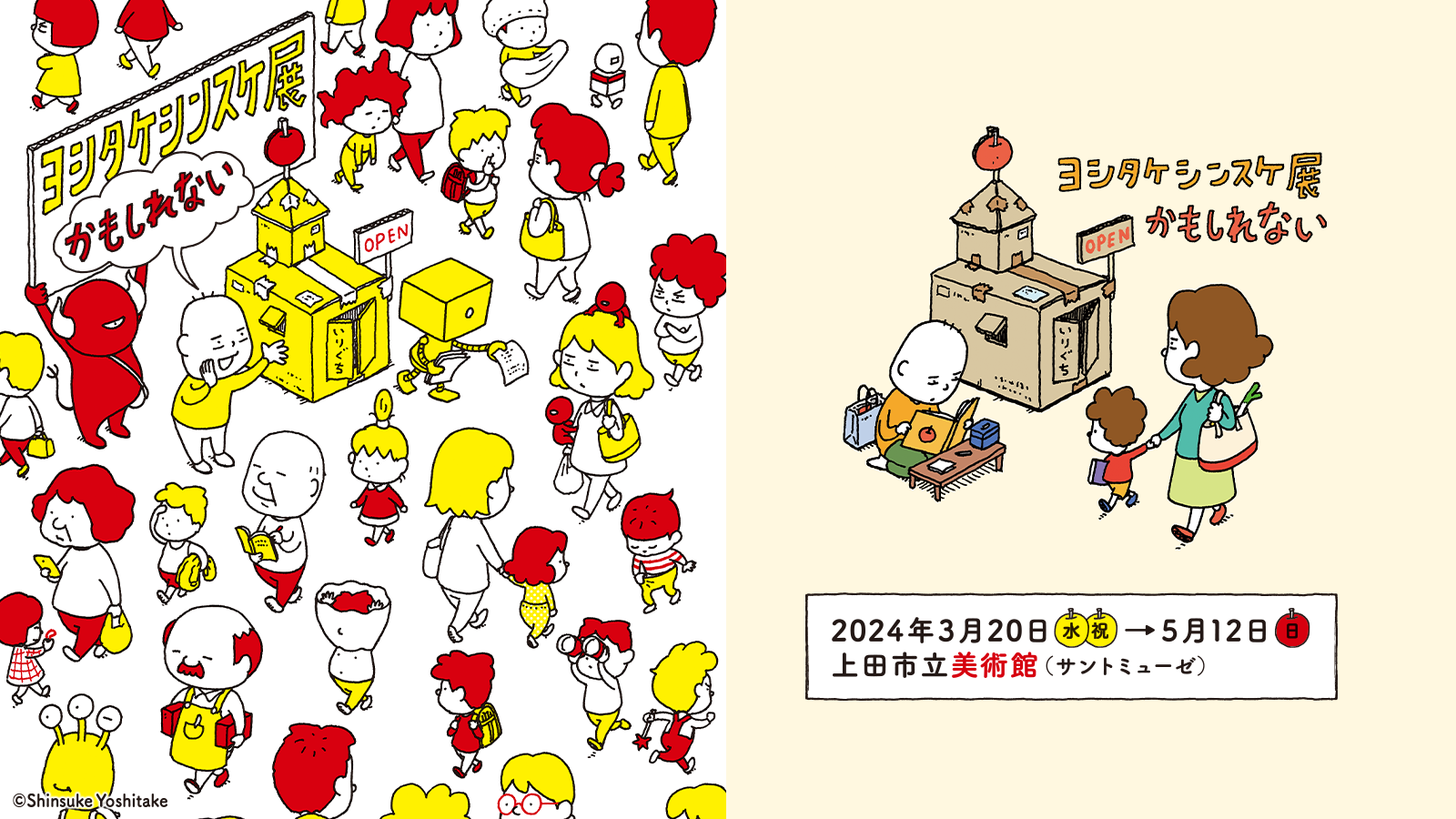【 レポート 】ミュージアムトーク 画家・米津福祐が語る雷電為右衛門の魅力
- 会場
- サントミューゼ
2020年9月5日(金)18:00~ at上田市立美術館企画展示室
ミュージアムトーク 画家・米津福祐が語る雷電為右衛門の魅力
お話 米津福祐 聞き手 小笠原正(当館学芸員)
現在開催中の上田市立美術館コレクション展Ⅱ「芸術家が捉えた躍動の美」では、スポーツや相撲にまつわる作品が展示されています。ライフワークとして20年以上にわたり、力士・雷電為右衛門を描いている画家・米津福祐さん自身が、作品や制作背景について語る、ミュージアムトークが行われました。
今回は、新型コロナウイルス感染症対策として密集を防ぐためにも、事前に申込みされた方々限定の夜間開館で、展示室の中に座り、作品に囲まれながらお話を伺うという、贅沢なひとときとなりました。

トークは、小笠原学芸員による米津さんのエッセイの朗読からはじまりました。『写生日和』という本の一節で、米津さんが両国橋で思索にふけっていると雷電がやってくる、という白昼夢のお話です。
そして、「雷電を描く以前は家族を描いたりしていたが、なぜ雷電を描くようになったのか、そのあたりをお聞かせ願えますか。」とマイクを向けました。
お話は、米津さんの若かりし頃から始まりました。
「私は商売をしていたので時間がなかった、朝8時半までの2時間 夜9時以降の3時間、誰にも迷惑をかけないようにと、昼間絵を描いたことはなかった」と語り始めた米津さん。子どもをどこかにつれていくとか、勉強をみてやることが一切なかったが、子どもにできない分、絵の世界で子どもと遊んでいて、いつの間にか家族を描いていたといいます。
「こういうと苦労話のようだが、全然苦労じゃなかった。面白くて、いつでも充実感があった」と楽しそうに語る米津さん。

そこから主題が雷電にうつったのは、二紀会の委員(審査員)になった頃のこと。日ごろから、この人の理想像を描きたいなという人で、誰もが知っている雷電為右衛門を、なんのためらいもなく描いたそうです。
「雷電為右衛門は天下無双、日本中であれ以上強い人がいない。そして調べれば調べるほどいい人なんですよ、ただ強いだけじゃない」と、雷電にまつわるエピソードや、その魅力を語っていきます。
雷電は、東御市に生まれましたが、14歳の頃、相撲好きで隣村(現上田市長瀬)にいた庄屋上原源右衛門が引き取り、相撲ばかりでなく四書五経まで学ばせたといいます。
その後雷電は、23歳で力士となりますが、地方巡業などでもずっと日記を書いていました。その日記は一般には「雷電日記」と呼ばれていますが、「諸国相撲控帳」「萬御用覚帳」と題されたもので、当時の相撲界の資料としても貴重なものとなっています。
米津さんは、その雷電日記や赤坂報土寺梵鐘事件(大関になった雷電が、横綱小野川を投げ飛ばしてしまい、行司の勝負預かりとなった。息子が敗れたと思った小野川の母が自害してしまい、それに心を痛めた雷電が追善供養にと梵鐘と鐘楼を寄進したが、その梵鐘が蜀山人が図案を作ったもので、大変な人気を博したことにより幕府に咎められ、雷電は江戸払いになってしまうという事件)にも触れ、しかし「雷電の日記の中には、そうした自分が困ったことは一切書かれていないんです。」「すごいなあと思う。ますます好きになった。」といいます。

そして、会場に展示されている石井鶴三の作品に目をやると、話はさらに少年時代に遡ります。
「思い返してみると、小学校1年から高校まで、自分を指導してくれたのは、石井鶴三の彫塑研究会にでておられた自由画運動の影響を受けた先生だった」といいます。
戦前は、国民学校というのはすごく制約や規則があったそうです。そんな中、「絵の時間だけ、あの小さな紙の中にだけ自由はあるんだ、と小学校のときにつくづく感じた。」といいます。
絵は何をやってもいい、そのことを先生がよくやったねと認めてくれた。そうした経験から、「べつにいい絵を描くつもりはなく、描くことが楽しかった。それが、はっときがついたらいつの間にか83歳になっていた」と米津さん。

米津さんが雷電を描き始めた頃は、浮世絵師の勝川春亭の雷電像などを参考にしたそうです。まずは雷電と同時代の画家がどう考えていたのかを知るために、そうした絵を写すことから出発して、人のまねではない、写真でもできない、自分の表現を模索していったそうです。
そして、目の前に並ぶ作品にひとつひとつ言及して、《赤半纏雷電》2002年 では、赤色と肉体を合わせてみたいなと思い、写真ではありえない世界を描こうとしたこと、《力人雷電》2003年 では、屈辱の雷電為右衛門、悩みなどの心情を背景としたこと、《ライデンのカタチ》2010年 ではとにかく直線で作品をつくってみよう、という意思であったこと、《ライデン》2013年 では、ぐっと力を入れたときに驚くような筋肉が垣間見えるということを創造で描いたことなど、主題とともに手法の変遷などについても語られました。

その中で、「去年やった作品は一切見ない。おんなじ絵を描いているんじゃ意味がないというのが私の美的な考え。人からみたら、いつもおなじじゃないかとみんなには言われるが、自分としてはだんだん変わっていく」といいます。
そして、「写生でもそっくりな写生は意味がない。写生のなかに創造がなけりゃだめだし、創造だけでいいかっていうと写生がないとだめ、この両方があってはじめて前に進むんで、ものを写す作業の中に創造力がないと、絵は描いていて全然面白くない。」「創造力があるから自分のやりたいことができるわけで、その根底に、いい絵を描こうと思わない、自分が新しいところをいつもやっていることが面白い」と、温和な表情のなかに潜む熱い思いを語りました。

最後に小笠原学芸員が、「石井鶴三や山本鼎などは、私は作品や記録をとおしてしかその作家を見られないのですが、現代の作家の場合、その空間に作家がいて、その方の話や人となりを聴きながら作品が見られるというのは、現代の作品の魅力で、今ここが幸せな空間に感じます。」と、1時間に及ぶトークを締めくくりました。
【参考資料】「雷電為右衛門~学び舎の郷(長瀬村)~」上田市わがまち魅力アップ応援事業 雷電為右衛門実行委員会